「モームリで退職したけど、大丈夫なの?」「今まさにモームリを使おうとしているけど、このまま依頼していいの?」
2025年10月22日、退職代行サービス最大手の「モームリ」に警視庁の家宅捜索が入ったニュースを見て、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
実は、すでにモームリを使って退職した方は基本的に心配する必要はありません。退職という法律行為自体は有効だからです。
しかし、これから退職代行サービスを使おうとしている方、特にモームリを検討していた方は要注意です。今回の事件は、退職代行業界全体が抱える構造的な問題を浮き彫りにしました。
この記事を読むとわかること
この記事では、次の5つのポイントを徹底解説します。
✅ モームリ事件の全容:なぜ警視庁が動いたのか、違法とされた理由を法律的にわかりやすく解説
✅ 利用者への具体的な影響:すでに利用した人、現在進行中の人、これから利用予定の人それぞれへの影響
✅ 安全な退職代行の見分け方:合法と違法の境界線、避けるべき業者の特徴を具体的に紹介
✅ 信頼できる退職代行サービス一覧:弁護士運営・労働組合運営の安全なサービスを厳選
✅ 自分で退職する方法も含めた完全ガイド:退職代行を使わない選択肢も含めて総合的に解説
「会社を辞めたいけど言い出せない」「上司からのパワハラで精神的に追い詰められている」――そんな悩みを抱えている方にこそ、読んでいただきたい記事です。
間違った退職代行サービスを選んでしまうと、お金を払ったのに退職できない、会社との関係がかえって悪化する、未払いの給与や残業代を請求できなくなる、といったリスクがあります。
この記事を最後まで読めば、安全に、確実に、そして後悔なく退職するための知識がすべて手に入ります。
3分で読める内容にまとめましたので、ぜひ最後までご覧ください。
モームリになにがあった?事件の全容
【結論】2025年10月22日、退職代行サービス最大手「モームリ」に警視庁が家宅捜索を実施。容疑は弁護士法違反(非弁行為)です。弁護士に依頼者を違法にあっせんし、紹介料を受け取っていた疑いがあります。すでに利用した方は基本的に問題ありませんが、これから利用予定の方は他社への切り替えを強く推奨します。
【速報】モームリに警視庁が家宅捜索
2025年10月22日午前9時過ぎ、東京都品川区にある退職代行サービス「モームリ」の運営会社・株式会社アルバトロスの本社に、警視庁の捜査員が次々と入っていきました。
この日、警視庁は約100人態勢で、モームリ本社だけでなく、提携する都内の複数の弁護士事務所にも一斉に家宅捜索を実施。容疑は弁護士法違反です。
報道陣が現場に駆けつける中、段ボール箱に詰められた資料が次々と運び出されていく光景が映し出されました。わずか3年で累計4万人以上が利用し、退職代行業界のトップを走っていたモームリに、なにがあったのでしょうか。
警視庁の捜査関係者によると、モームリは退職代行の仕事を違法に弁護士にあっせんし、その見返りとして紹介料(キックバック)を受け取っていた疑いがあるとのこと。これは弁護士法で明確に禁止されている「非弁行為」に該当する可能性が高い行為です。
今回の捜査では、関係者数十人から事情を聴く方針で、押収した資料を詳しく分析して刑事責任を問えるかどうか調べを進めています。
モームリが違法とされた理由
なぜモームリは違法とされたのか。この問題を理解するには、まず「非弁行為」という言葉を知る必要があります。
非弁行為とは何か?
非弁行為とは、弁護士の資格を持っていない人が、お金をもらう目的で法律に関する仕事をすることです。弁護士法第72条と第27条で厳しく禁じられています。
なぜこんな法律があるのでしょうか。それは戦後の混乱期に「事件屋」と呼ばれる悪質な業者が横行し、法律の知識がない人たちが高額な費用を請求されたり、不利な契約を結ばされたりする被害が続出したからです。
モームリの違法行為の仕組み
モームリが行っていたとされる違法行為は、次のような流れでした。
まず、依頼者がモームリに退職代行を依頼します。退職を進める過程で、給与の未払いや残業代の請求、有給休暇の交渉など、法律が絡む問題が出てきた場合、モームリは「これは法律問題なので弁護士が必要です」と判断。
そこで提携している弁護士を「特別価格」として紹介し、依頼者は新たに弁護士と契約を結びます。この時点で、依頼者はモームリと弁護士への二重払いが発生しているわけです。
問題はこの後です。弁護士がその報酬の一部をモームリに紹介料として支払っていたとされます。これが弁護士法第27条で禁止されている「報酬を得る目的での法律事務のあっせん」に該当するのです。
利用者にとっての実害
この仕組みの何が問題なのでしょうか。
第一に、紹介料が上乗せされることで、利用者が支払う金額が不当に高くなります。本来であれば弁護士に直接依頼すればよいのに、モームリを通すことで余計な費用が発生していたのです。
第二に、法律の専門知識がない業者が間に入ることで、利用者にとって不利な契約を結んでしまうリスクがあります。もしトラブルが起きても、責任の所在が曖昧になり、利用者が泣き寝入りするケースも考えられます。
東京弁護士会の小町谷悠介弁護士は、このような指摘をしています。
「残業代の問題とか、退職に伴う法的な問題が発生したときに、それを弁護士資格のない退職代行の業者さんがそういった話を突っ込んでしてしまうと非弁行為ということで、違法になる可能性があります」
警視庁は、モームリでは「非弁行為」にあたる法律に関わる交渉が行われている実態を把握しているとのことで、今後さらに詳しく調べを進める方針です。
事件の予兆:週刊文春が半年前に報道
実は、今回の警視庁による家宅捜索の半年前、2025年4月16日に週刊文春がモームリの問題を詳しく報じていました。
元従業員の衝撃的な告発
週刊文春の記事で最も衝撃的だったのは、元従業員のこんな証言でした。
「モームリで働くことが『モームリ!』になり、他の退職代行を使って辞める人が後を絶ちません。すでに5人が退職代行を利用して辞めています」
退職代行サービスを提供する会社の従業員が、他社の退職代行を使って辞めるという、極めて皮肉な状況が明らかになったのです。普通であれば、自社のサービスを使えばいいはずなのに、なぜわざわざ他社を使ったのでしょうか。
元従業員の一人は、取材に対してこう語っています。
「違法行為を口外しないように言われていました。社員全員の前で『完全に違法だと把握している』という雰囲気がありました」
社内では法律違反の疑いがあることを認識しながら、それを隠して事業を続けていた可能性が高いのです。
谷本慎二社長のパワハラ疑惑
週刊文春の記事では、創業者である谷本慎二社長(35歳)によるパワハラ疑惑も報じられました。
過度なノルマの設定、深夜まで続く会議、タイピング音がうるさいといった些細なことでの叱責など、職場環境に問題があったとの証言が複数出ています。
「会社を辞めたくても辞められない」という悩みを抱える人を助けるはずの退職代行サービスの会社で、従業員自身が「辞めたくても辞められない」状況に追い込まれていたとすれば、これほどの矛盾はありません。
弁護士からのキックバック疑惑
週刊文春が報じたもう一つの重要なポイントが、弁護士からのキックバック疑惑です。
モームリは公式サイトで「労働事件に強い顧問弁護士をご紹介」とうたっていましたが、その紹介によって弁護士から紹介料を受け取っていた疑いがあるとされました。
これに対してモームリ側は、「我々はあくまで依頼者の退職の意思を伝えているだけであり、法律業務は弁護士に任せるので交渉はしていない」と説明していました。
しかし、元従業員は「モームリは非弁行為とは別の法律違反の疑いがあるのです」と話しており、週刊文春の報道から半年後、ついに警視庁が動いたのです。
モームリとは?3年で4万人利用の急成長企業
そもそもモームリとは、どんな会社だったのでしょうか。
驚異的な成長スピード
モームリは2022年3月にサービスを開始しました。創業者の谷本慎二社長は、前職のサービス業で過酷な労働環境を経験し、「退職に悩む人を助けたい」という思いから起業したと語っています。
創業時は谷本社長一人でスタートしましたが、わずか3年で従業員は50名以上、累計利用者数は4万人を突破。2025年1月期の売上高は3億3000万円に達し、業界シェア7割とも言われるまでに成長しました。
サービス開始から右肩上がりの業績は、谷本社長自身が「大爆発」と表現するほどの勢いでした。
若者に圧倒的な支持
モームリの利用者の特徴は、その若さです。
利用者の約6割が20代、さらに30代を加えると全体の8割以上を占めます。就職氷河期やコロナ禍を経験した若い世代にとって、「会社を辞めたい」と自分で言い出せない状況は、決して珍しくありません。
特に新卒社員の利用が多く、入社から3ヶ月以内の利用が全体の44%を占めていました。「入社前の説明と実際の仕事が違う」「上司からハラスメントを受けている」といった理由が上位を占めています。
シンプルでわかりやすい料金設定
モームリの料金は、正社員・契約社員が22,000円、パート・アルバイトが12,000円と、業界の中では比較的リーズナブルな設定でした。
24時間365日、LINEや電話で相談を受け付け、即日対応も可能。退職できなかった場合は全額返金という保証もあり、利用者にとっては安心感がありました。
積極的なメディア展開
モームリが急成長できた理由の一つが、積極的なメディア展開です。
日本テレビの「シューイチ」をはじめ、多くの情報番組に取り上げられ、2024年4月以降だけで500社以上のメディアから取材を受けました。谷本社長自身も、YouTubeチャンネル「令和の虎」やABEMAの「アベマプライム」など、注目度の高い番組に出演。
街中を走る宣伝トラックも話題になり、「もう無理」という名前のキャッチーさも相まって、SNSでの拡散も進みました。
事業の多角化
モームリは退職代行だけでなく、事業の多角化も進めていました。
年間2万件以上蓄積される退職データを活用した「MOMURI+(モームリプラス)」という企業向けコンサルティングサービス、自分で退職を伝えたい人向けの「セルフ退職ムリサポ!」、Web上の情報収集を代行する「検索代行モーシラン」など、複数のサービスを展開していました。
しかし、その急成長の裏側で、今回のような法律違反の疑いが指摘されていたのです。
【オリジナル視点】退職代行会社が退職代行を使われる矛盾
モームリの事件を読み解く上で、見逃せないのが「退職代行会社の従業員が、他社の退職代行を使って辞める」という究極の矛盾です。
5人が退職代行で退職という異常事態
通常、退職代行サービスを提供する会社であれば、自社のサービスを使えばスムーズに退職できるはずです。それなのに、なぜ従業員はわざわざお金を払って他社のサービスを使ったのでしょうか。
これは、社内の環境があまりにも悪く、自分で退職を切り出すことも、自社のサービスを使うこともできない状況だったことを物語っています。
元従業員の証言によると、社内では「違法行為を口外するな」という指示があり、問題を外部に漏らすことへの恐怖があったとされます。自社サービスを使えば、その事実が社内に広まることを恐れたのかもしれません。
ビッグモーター事件との構造的類似性
この状況は、2023年に大きな社会問題となったビッグモーター事件と驚くほど似ています。
第一に、急成長の陰に無理があったという点です。モームリは3年で業界トップに躍進し、ビッグモーターも短期間で全国展開を果たしました。急激な成長の裏には、無理なノルマや違法行為の黙認があったのではないでしょうか。
第二に、サービス内容の不透明性です。ビッグモーターでは整備現場で不正が行われても、顧客は裏側を知ることができませんでした。退職代行も、依頼者には「無事に辞められた」という結果しかわからず、その過程はブラックボックスになっています。
第三に、成果至上主義と組織的隠蔽です。ビッグモーターは過剰なノルマのもとで不正を黙認する空気が生まれました。モームリでも元社員が「違法行為を口外するな」と指示されていたと証言しており、組織的に違法な手法を隠していた疑いがあります。
「人を助ける事業」の落とし穴
モームリのような「人を助ける」ことを掲げる事業は、その理念の素晴らしさゆえに、内部の問題が見えにくくなるという特徴があります。
「退職に悩む人を救う」という大義名分があるため、多少の無理や違法行為も「困っている人のためだから」と正当化されやすいのです。
しかし、その結果として従業員が疲弊し、助けるはずの依頼者も結果的に高額な費用を支払わされる。こうした矛盾が積み重なった結果が、今回の家宅捜索という事態につながったと言えるでしょう。
モームリ利用者への影響は?
「自分がモームリを使って退職したけど、大丈夫なの?」「今まさに利用中だけど、どうすればいい?」
そんな不安を抱えている方も多いはずです。ここでは、利用者への影響について詳しく解説します。
すでに退職が完了している人:基本的に問題なし
まず安心してください。すでにモームリを利用して退職が完了している人については、基本的に問題ありません。
退職という法律行為そのものは有効です。たとえ退職代行業者に法律違反があったとしても、あなたの退職が無効になることはありません。会社から「やっぱり退職は認めない」と言われる心配もないのです。
ただし、退職時に未払いの給与や残業代、有給休暇の買い取りなど、金銭的な問題が未解決のまま残っている場合は注意が必要です。
モームリが今後業務を継続できるかどうか不透明な状況ですので、金銭的な問題がある場合は、早めに弁護士や労働基準監督署に相談することをおすすめします。
現在進行中の人:状況確認が必要
現在モームリを利用していて、退職手続きが進行中という方は、まずモームリに連絡を取って状況を確認してください。
警視庁の家宅捜索が入ったからといって、すぐに業務がストップするわけではありません。ただし、今後の捜査の進展によっては、サービスが停止する可能性もあります。
もし連絡が取れない、対応が遅いなどの問題があれば、以下のような対応を検討しましょう。
- 他の信頼できる退職代行サービス(弁護士運営または労働組合運営)への切り替え
- 自分で会社に連絡を取る
- 労働基準監督署や弁護士会の法律相談を利用する
これから利用を予定していた人:他社の検討を強く推奨
これからモームリの利用を検討していた方は、現時点では他社の利用を検討することを強くおすすめします。
今後の捜査の進展によっては、モームリのサービスが停止したり、会社そのものが営業できなくなったりする可能性があります。そうなると、支払った料金が返金されない、途中でサービスが受けられなくなるといったリスクがあるのです。
退職代行サービスを利用する際は、弁護士が運営するサービスか、労働組合が運営するサービスを選ぶことが安全です。後ほど詳しく解説しますが、これらのサービスであれば法律的に問題なく、安心して利用できます。
返金対応の可能性について
モームリは「退職できなかった場合は全額返金」を保証していましたが、今回の事件を受けて返金を求めたい場合はどうすればいいのでしょうか。
まずはモームリに直接連絡を取り、返金を求めることになります。ただし、会社の状況によっては返金に応じてもらえない可能性もあります。
その場合は、以下の方法が考えられます。
- クレジットカード決済の場合:カード会社にチャージバック(取引の取り消し)を申請
- 銀行振込の場合:消費生活センターや弁護士に相談
- 少額訴訟の検討(60万円以下の金銭トラブルの場合)
いずれにしても、やり取りの記録(LINEのスクリーンショット、メール、契約書など)は必ず保存しておきましょう。
モームリ事件で何が変わる?退職代行業界への影響
【結論】今回の事件により、退職代行業界全体に法規制強化の動きが予想されます。違法な業者は淘汰され、弁護士運営・労働組合運営の適法サービスへの移行が進むでしょう。利用者は必ず運営形態を確認し、「提携弁護士」を前面に出す一般企業運営のサービスは避けるべきです。最も安全なのは、弁護士が直接運営するサービスです。
東京弁護士会が声明を発表
モームリへの家宅捜索を受けて、東京弁護士会は2025年10月22日、退職代行サービスに関する声明を発表しました。
声明では、退職代行サービスの一部に「非弁行為」に該当する可能性のある業者が存在することを指摘。業界全体に対して注意を喚起する内容となっています。
東京弁護士会は以前から、退職代行サービスについてのガイドラインを公表しており、今回の事件を受けて過去のブログ記事「退職代行サービスと弁護士法違反」を再度紹介。非弁行為について詳しく説明しています。
同業他社の反応と対応
モームリの報道を受けて、他の退職代行業者も相次いで声明を発表しました。
退職代行「ガーディアン」を運営する東京労働経済組合(TRK)は、「当組合は労働組合法に基づき、法令を順守した完全合法の退職代行サービスを行っている」とプレスリリースを発表。
退職代行「EXIT」を運営するEXITの新野俊幸社長も、自身のXアカウントで「弊社は退職代行のパイオニアとして、弁護士法を順守しています」と投稿しました。
各社とも、「自分たちは違う」というアピールに必死な様子がうかがえます。しかし、果たして本当に安全なのでしょうか。
合法な退職代行の見分け方
退職代行サービスには、大きく分けて3つの運営形態があります。それぞれできることと、できないことが法律で明確に決まっています。
弁護士が運営:すべての対応が可能
弁護士が運営する退職代行サービスは、法律的にすべての対応が可能です。
退職の意思を伝えるのはもちろん、残業代の請求、退職金の交渉、有給休暇の買い取り交渉、パワハラの損害賠償請求など、あらゆる法律問題に対応できます。
さらに、会社とトラブルになって裁判になった場合でも、そのまま代理人として対応してもらえます。
料金は5万円〜7万円程度と高めですが、確実性と安心感は最も高いと言えるでしょう。
労働組合が運営:交渉までは可能
労働組合が運営する退職代行サービスは、会社との交渉まで対応できます。
労働組合には「団体交渉権」という法律で認められた権利があり、会社側はこれを拒否できません。退職日の調整、有給休暇の取得、未払い給与の請求などの交渉が可能です。
ただし、裁判の代理人にはなれません。もし裁判になった場合は、別途弁護士に依頼する必要があります。
料金は2.5万円〜3万円程度で、弁護士よりもリーズナブルです。多くの退職ケースでは、裁判まで行くことは少ないため、労働組合運営のサービスでも十分対応できることが多いでしょう。
一般企業が運営:伝達のみ(モームリはこれ)
株式会社などの一般企業が運営する退職代行サービスは、法律上は「退職の意思を伝えるだけ」しかできません。
モームリはこのタイプでした。会社との交渉は一切できず、あくまでも依頼者の言葉を会社に伝える「使者」としての役割に限定されます。
もし会社から「退職は認めない」「損害賠償を請求する」などと言われた場合、一般企業の退職代行サービスは何もできません。依頼者自身が対応するか、別途弁護士に依頼する必要があるのです。
料金は2万円〜3万円程度と最も安いですが、トラブルが起きた時のリスクも最も高いと言えます。
安全な業者を選ぶ5つのチェックポイント
では、具体的にどうやって安全な退職代行サービスを見分ければいいのでしょうか。次の5つのポイントをチェックしてください。
- 運営形態が明確に記載されている 公式サイトに「弁護士運営」「労働組合運営」「一般企業運営」のいずれかが明記されているか確認しましょう。
- 対応範囲が明確 「何ができて、何ができないか」がはっきり書いてあるかチェック。「何でもできます」と書いてある一般企業は要注意です。
- 料金体系が明確 基本料金、追加料金の有無、返金保証の条件などが明記されているか確認しましょう。
- 実績と口コミ 創業年数、対応件数、第三者の口コミサイトでの評価を確認。極端に安い料金や、口コミが少ない業者は避けた方が無難です。
- 会社情報が明確 運営会社の住所、電話番号、代表者名が公式サイトに記載されているか確認。情報が不明瞭な業者は信頼できません。
避けるべき業者の特徴
逆に、次のような特徴がある業者は避けるべきです。
- 運営形態が不明確(弁護士・労働組合・一般企業のいずれか書いていない)
- 一般企業なのに「交渉できます」と書いてある
- 料金が異常に安い(1万円以下など)
- 「提携弁護士」を前面に押し出している(これがモームリと同じパターン)
- 会社情報が不明瞭
- 口コミが極端に少ない、または悪い評価が目立つ
特に注意すべきは「提携弁護士がいるから安心」という表現です。これはモームリと同じパターンで、結局は一般企業が運営していて、法律問題が起きたら別途費用を払って弁護士に依頼する必要があるケースがほとんどです。
退職代行の違法ラインはどこ?
退職代行サービスの合法と違法の境界線は、実は非常にシンプルです。
✅ 合法な行為:退職の意思を伝える
弁護士資格がなくても、以下のことは合法です。
- 依頼者の退職の意思を会社に伝える
- 退職日の確認
- 必要な書類(離職票、源泉徴収票など)の確認
- 会社からの貸与品の返却方法の確認
- 私物の返却方法の確認
これらはあくまでも「事実を伝える」「確認する」という行為であり、法律的な判断や交渉は含まれていません。
❌ 違法になる行為:交渉や法律判断
一方で、弁護士資格がない者が以下のことを行うと、違法になります。
- 残業代の金額交渉
- 退職金の金額交渉
- 有給休暇の買い取り交渉
- 退職日の交渉(会社が認めない場合の説得)
- 損害賠償請求への対応
- その他、法律的な判断を伴う交渉
グレーゾーンの具体例
実際の現場では、合法と違法の境界線が曖昧なケースも多くあります。
例えば、「有給休暇の日数を教えてください」と会社に聞くのは合法です。しかし、「有給休暇を消化させてください」と交渉するのは違法の可能性があります。
「退職日はいつになりますか?」と確認するのは合法ですが、会社が「2ヶ月後にしてほしい」と言った時に「いや、2週間後にしてください」と交渉するのは違法の可能性があるのです。
このグレーゾーンがあるため、一般企業の退職代行サービスは常に法律違反のリスクと隣り合わせなのです。
「提携弁護士」の落とし穴
モームリの事件で明らかになったのが、「提携弁護士」という仕組みの落とし穴です。
「提携弁護士がいるから安心」という表現は、一見すると問題なさそうに見えます。しかし実態は、次のような問題があります。
- 二重払いの問題 依頼者は退職代行業者と弁護士の両方に料金を払うことになり、合計金額が高額になります。
- あっせんの問題 業者が弁護士を紹介して紹介料を受け取ると、今回のモームリのように弁護士法違反になる可能性があります。
- 責任の所在が不明確 トラブルが起きた時、退職代行業者と弁護士のどちらに責任があるのか曖昧になります。
本当に安心したいなら、最初から弁護士が直接運営している退職代行サービスを選ぶべきです。
モームリ以外も危ない?業界の実態
今回のモームリの事件は、決して他人事ではありません。業界全体に同様の問題が潜んでいる可能性があります。
EXIT、SARABA、Jobsなども同様の指摘
実は、モームリだけでなく、業界大手と言われる他のサービスにも同様の指摘があります。
退職代行「EXIT」「SARABA」「Jobs」「やめたらええねん」「ヤメドキ」「オイトマ」「辞めるんです」など、株式会社が運営する退職代行サービスの多くが、労働組合と提携して「交渉できます」とうたっています。
しかし、労働組合法人である退職代行ガーディアンは、Xで「事件屋」という言葉を用いて、こうした業者の問題点を指摘しています。
株式会社運営の退職代行が抱えるリスク
株式会社が運営する退職代行サービスの構造的な問題は、次の通りです。
第一に、本来は「伝達のみ」しかできないはずなのに、実際には交渉まで踏み込んでいるケースが多いこと。表向きは「提携労働組合が交渉する」と説明していても、実態は会社の従業員が対応しているケースもあるとされます。
第二に、利益追求の圧力が強いこと。株式会社は利益を上げることが最優先されるため、どうしても無理なケースでも「絶対に辞められます」と請け負ってしまう傾向があります。
第三に、トラブル時の対応力が弱いこと。会社が「退職は認めない」「損害賠償を請求する」などと強硬な姿勢を取った場合、株式会社の退職代行は何もできません。
退職成功率100%は本当か?
多くの退職代行サービスが「退職成功率100%」と宣伝していますが、これは本当なのでしょうか。
実は、この数字には大きな落とし穴があります。
まず、「退職できなかった」ケースはカウントされていない可能性があります。途中で連絡が取れなくなった、自分で会社に連絡を取ることになったなど、サービスとして完結しなかったケースは統計に含まれていないのです。
また、法律的には退職の意思表示をすれば2週間後には退職できるため、最終的にはほとんどのケースで退職自体は可能です。問題は、その過程でトラブルが起きないか、残業代などの権利がきちんと守られるかという点なのです。
失敗したらどうなる?
もし退職代行サービスを使って失敗したら、どうなるのでしょうか。
最悪のケースは、次のような状況です。
- 料金を払ったのに退職できず、自分で会社に連絡を取らなければならなくなる
- 会社との関係が余計に悪化し、退職交渉が困難になる
- 有給休暇の権利を失う
- 未払いの給与や残業代を請求できなくなる
- 返金されない
こうしたリスクを避けるためにも、最初から信頼できる業者を選ぶことが重要なのです。
今後の退職代行業界はどうなる?
今回のモームリの事件は、退職代行業界に大きな変化をもたらすと予想されます。
法規制強化の可能性
現在、退職代行サービスに関する明確な法律はありません。弁護士法や労働組合法、労働基準法などの既存の法律で対応しているのが実情です。
しかし、今回の事件を受けて、退職代行サービスを規制する新しい法律が作られる可能性があります。
例えば、以下のような規制が考えられます。
- 退職代行業の登録制度の導入
- 一般企業が運営する場合の業務範囲の明確化
- 料金の上限設定
- 誇大広告の禁止
- 利用者保護のための仕組み
業界の淘汰と再編
法規制が強化されれば、違法性のある業者は淘汰されていくでしょう。
特に、「提携弁護士」や「提携労働組合」という曖昧な形で法律の抜け道を使っている業者は、事業の継続が困難になる可能性があります。
一方で、最初から弁護士や労働組合が直接運営している適法なサービスは、信頼性が高まり、利用者が増えることが予想されます。
結果として、業界全体が健全化し、利用者にとってより安全なサービスが提供されるようになるでしょう。
適法サービスへの移行
すでに一部の業者は、今回の事件を受けて事業形態の見直しを始めています。
株式会社から労働組合への組織変更、弁護士との正式な提携関係の構築など、より適法な形でのサービス提供を模索する動きが出ています。
また、弁護士会や労働組合が、退職代行サービスの適正化に向けたガイドラインを作成する動きも出てくるでしょう。
利用者が知っておくべきこと
今後、退職代行サービスを利用する際に知っておくべきことは、次の通りです。
- 安さだけで選ばない 料金の安さに惹かれて一般企業の退職代行を選ぶと、結局トラブルが起きて弁護士に依頼し直すことになり、かえって高くつく可能性があります。
- 運営形態を必ず確認する 弁護士運営か、労働組合運営か、一般企業運営かを必ず確認しましょう。
- 口コミだけを信じない ネット上の口コミは操作されている可能性もあります。複数の情報源を確認しましょう。
- 契約内容をよく読む 返金保証の条件、対応範囲、追加料金の有無などを契約前に必ず確認しましょう。
- 記録を残す やり取りはすべて記録に残しておきましょう。LINEのスクリーンショット、メールの保存などが重要です。
【実用情報】安全に退職するための完全ガイド
最後に、安全に退職するための実用的な情報をまとめてお伝えします。
信頼できる退職代行サービス一覧
〈弁護士運営トップ3〉
- 弁護士法人みやび
- 料金:55,000円
- 特徴:24時間相談受付、全国対応、残業代・退職金請求も対応可能
- 実績:多数の対応実績あり
- 弁護士法人響
- 料金:55,000円
- 特徴:弁護士が直接対応、裁判対応も可能
- 実績:労働問題に特化した弁護士事務所
- 汐留パートナーズ法律事務所
- 料金:54,000円
- 特徴:企業法務に強い、丁寧な対応
- 実績:大手企業の退職案件も多数
〈労働組合運営トップ3〉
- 退職代行ガーディアン
- 料金:29,800円
- 特徴:東京労働経済組合が運営、団体交渉が可能
- 実績:月間1,000〜1,500件の相談
- 退職代行SARABA
- 料金:24,000円
- 特徴:労働組合が対応、24時間受付
- 実績:5,000件以上の退職実績
- わたしNEXT
- 料金:29,800円(女性専用)
- 特徴:女性の退職に特化、丁寧な対応
- 実績:女性の退職案件に強み
※料金は2025年10月時点の情報です。最新情報は各社の公式サイトでご確認ください。
自分で退職を伝える方法
可能であれば、自分で退職を伝えるのが最も確実で費用もかかりません。以下の手順で進めましょう。
ステップ1:退職の意思決定(退職希望日の1〜3ヶ月前)
- 自分のキャリアプランを整理
- 次の仕事の目途を立てる
- 貯金を確認
ステップ2:直属の上司に相談(退職希望日の1〜2ヶ月前)
- まずは口頭で相談
- 「相談があるのですが」と切り出す
- 退職理由は前向きに(キャリアアップなど)
ステップ3:退職届の提出(退職希望日の1ヶ月前)
- 会社指定の書式があれば使用
- なければ自分で作成
- 提出日と退職希望日を明記
ステップ4:引き継ぎ(退職日まで)
- 業務のマニュアル作成
- 後任者への引き継ぎ
- 取引先への挨拶
ステップ5:退職手続きの完了
- 離職票の受け取り
- 源泉徴収票の受け取り
- 健康保険証の返却
円満退職のコツ
- 感謝の気持ちを伝える
- 引き継ぎを丁寧に行う
- 最後まで手を抜かない
- SNSで会社の悪口を書かない
労働基準監督署への相談方法
パワハラや未払い賃金など、違法な状況にある場合は、労働基準監督署に相談できます。
相談できる内容
- 賃金の未払い
- サービス残業
- 違法な長時間労働
- パワハラ・セクハラ
- 不当な解雇
相談の手順
- 最寄りの労働基準監督署を調べる(厚生労働省のサイトで検索可能)
- 電話で相談予約を取る
- 証拠を持って相談に行く
- タイムカードのコピー
- 給与明細
- パワハラの録音や記録
- 就業規則のコピー
相談は無料 労働基準監督署への相談は無料です。匿名での相談も可能ですが、具体的な対応を求める場合は実名での相談が必要になります。
パワハラ・未払い賃金の対処法
パワハラの証拠を集める
- 暴言の録音
- メールやLINEのスクリーンショット
- 日記(日時、場所、内容を記録)
- 診断書(精神的苦痛がある場合)
未払い賃金の証拠を集める
- タイムカードのコピー
- 日報や業務記録
- 給与明細
- 雇用契約書
対処の手順
- まずは会社に書面で請求
- 応じない場合は労働基準監督署に相談
- それでもダメなら弁護士に相談
- 労働審判や訴訟を検討
時効に注意 賃金の未払いは2年(当分の間は3年)、パワハラの損害賠償は3年で時効になります。早めの行動が重要です。
まとめ
2025年10月22日、退職代行業界最大手の一つであるモームリに警視庁の家宅捜索が入りました。容疑は弁護士法違反、具体的には弁護士への違法なあっせんとキックバックの受領です。
この事件は、急成長する退職代行業界が抱える構造的な問題を浮き彫りにしました。「人を助ける」という大義名分のもとで、実は法律違反のグレーゾーンで事業を展開していた実態が明らかになったのです。
モームリを利用した方、特にすでに退職が完了している方は基本的に心配する必要はありません。ただし、現在進行中の方や、これから利用を予定していた方は、他の信頼できるサービスへの切り替えを検討すべきでしょう。
退職代行サービスを選ぶ際は、必ず運営形態を確認してください。弁護士が直接運営しているサービス、または労働組合が直接運営しているサービスを選べば、法律的に問題なく安心して利用できます。
一般企業が運営する退職代行サービス、特に「提携弁護士」を前面に出しているサービスには注意が必要です。今回のモームリの事件が、まさにその問題点を示しています。
可能であれば、自分で退職を伝えることが最も確実で費用もかかりません。しかし、どうしても自分では言い出せない、パワハラで精神的に追い詰められているなどの事情がある場合は、信頼できる退職代行サービスを利用するのも一つの選択肢です。
大切なのは、安さだけで選ばないこと。最初は安く見えても、トラブルが起きて弁護士に依頼し直すことになれば、かえって高くつきます。最初から適法なサービスを選ぶことが、結果的に最も安全で確実な方法なのです。
今回の事件をきっかけに、退職代行業界全体がより健全化し、本当に困っている人が安心して利用できるサービスへと進化していくことを願っています。
【総括】モームリになにがあったのか?重要ポイントまとめ
モームリ事件の全容
- 2025年10月22日、警視庁が約100人態勢でモームリ本社と複数の弁護士事務所に家宅捜索を実施
- 容疑は弁護士法違反(非弁行為):弁護士に依頼者を違法にあっせんし、キックバック(紹介料)を受け取っていた疑い
- 週刊文春が半年前(2025年4月)に違法性を報道:元従業員5人が他社の退職代行を使って退職という皮肉な状況が発覚
- モームリは2022年創業から3年で4万人利用、売上3億円超、業界シェア7割の急成長企業だった
- 「退職代行会社の従業員が退職代行を使う」矛盾は、ビッグモーター事件と構造的に類似(成果至上主義と組織的隠蔽)
- すでに退職完了した利用者は基本的に問題なし。現在進行中の方は状況確認、これから利用予定の方は他社への切り替えを強く推奨
退職代行業界への影響と今後の対策
- 東京弁護士会が声明を発表:退職代行の非弁行為に警鐘、業界全体への注意喚起を実施
- 合法な退職代行の見分け方:①弁護士運営(すべて対応可能)、②労働組合運営(交渉まで可能)、③一般企業運営(伝達のみ)
- 退職代行の違法ライン:退職の意思を伝えるのは合法、残業代・退職金の交渉は弁護士資格がないと違法
- 「提携弁護士」の落とし穴:二重払い、あっせん違法、責任の所在が不明確という3つの問題がある
- モームリ以外も同様のリスク:EXIT、SARABA、Jobsなど株式会社運営の退職代行サービスにも同様の指摘あり
- 今後は法規制強化の可能性:業界の淘汰と再編が進み、適法サービス(弁護士・労働組合運営)への移行が加速する見込み
- 安全に退職するには:弁護士運営または労働組合運営のサービスを選ぶ、可能なら自分で退職を伝える、困った時は労働基準監督署へ相談
モームリ事件から学ぶべき教訓
- 安さだけで選ぶと結果的に高くつく:トラブル時に弁護士に依頼し直すことになり、二重払いになる可能性
- 「○○と提携」には要注意:一般企業が「提携弁護士」「提携労働組合」を前面に出す場合、モームリと同じパターンの可能性
- 運営形態の確認は必須:公式サイトに弁護士運営・労働組合運営・一般企業運営のいずれかが明記されているか必ず確認
- 口コミや成功率100%だけを信じない:記録を残し、契約内容をよく読み、複数の情報源を確認することが重要
- 本当に困っているなら適法なサービスを:弁護士が直接運営する退職代行なら、法律的にすべて対応可能で最も安全
最終更新日:2025年10月23日

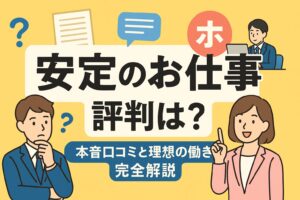
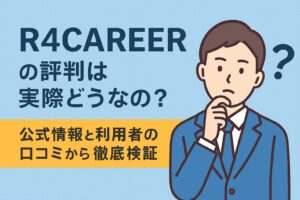


コメント