基本情報技術者の午前問題(科目A)で「どこから勉強すればいいかわからない」「効率的な合格法が知りたい」とお悩みではありませんか?
実は、約70%が過去問から出題されるという特徴を活かせば、3ヶ月の集中学習で確実に合格点を獲得できます。
この記事では、過去問道場の効果的な使い方から計算問題の攻略法、試験当日の時間配分戦略まで、実際に合格した受験者の体験談をもとに具体的な学習ロードマップを公開します。
文系出身者や数学が苦手な方でも実践できる方法ばかりです。記事を読み終える頃には、「これなら自分にもできそう」と自信を持って学習をスタートできるはずです。
3分で読める内容で、あなたの学習効率を劇的に向上させます。

基本情報技術者の午前問題(科目A)の基本情報と勉強法

基本情報技術者午前問題の概要と出題傾向
基本情報技術者の午前問題(科目A)は、IT業界で働く上で必要な基礎知識を問う重要な試験です。まず押さえておきたいのは、この試験の特徴として約70%が過去問から出題されるということ。つまり、過去問対策が合格への最短ルートと言えるでしょう。
ただし、単純に過去問を解けば良いというわけではありません。出題傾向を理解し、効率的に学習を進めることが重要になります。
科目A試験の基本情報(問題数・時間・合格基準)
科目A試験の基本的な構成は以下の通りです:
- 問題数:60問(全問必答)
- 試験時間:90分
- 出題形式:四肢択一(4つの選択肢から1つを選択)
- 配点:1000点満点
- 合格基準:600点以上(正答率60%以上)
90分で60問を解くということは、1問あたり約1.5分の計算になります。しかし実際には、多くの受験者が「時間が余った」と報告しており、時間的な余裕はある程度確保できると考えて良いでしょう。
例えば、2024年に合格したAさんは「基本的な知識問題なら30秒程度で解けるものが多く、計算問題に時間をかけても十分に見直し時間が確保できた」と話しています。
テクノロジ系・マネジメント系・ストラテジ系の出題割合
基本情報技術者の午前問題は、大きく3つの分野に分かれています:
1. テクノロジ系(約50問)
- 基礎理論(2進数、論理演算など)
- コンピュータシステム(ハードウェア、ソフトウェア)
- 技術要素(データベース、ネットワーク、セキュリティ)
- 開発技術(アルゴリズム、プログラミング)
2. マネジメント系(約5問)
- プロジェクトマネジメント
- サービスマネジメント
3. ストラテジ系(約5問)
- システム戦略
- 経営戦略
- 企業と法務
テクノロジ系が圧倒的な比重を占めているため、まずはこの分野を重点的に学習することが合格への近道となります。
2023年の試験制度変更点(午前→科目A)
2023年4月から実施された主な変更点をまとめると以下のようになります:
変更前(午前試験)
- ペーパーテスト方式
- 年2回実施(春期・秋期)
- 80問、150分
変更後(科目A試験)
- CBT(コンピュータ基盤テスト)方式
- 通年実施(いつでも受験可能)
- 60問、90分
特に注目すべきは、CBT方式の導入によりいつでも受験できるようになったことです。これにより、自分のペースで学習を進め、準備が整ったタイミングで受験することが可能になりました。
基本情報技術者午前問題の効率的な勉強法
基本情報技術者の午前問題で確実に合格するためには、やみくもに勉強するのではなく、戦略的なアプローチが必要です。特に重要なのは「過去問中心の学習」と「弱点分野の集中対策」の2点。
ここでは、多くの合格者が実践している効率的な勉強法を段階別に解説いたします。
初心者向け参考書の選び方(キタミ式、出るとこだけ等)
参考書選びは合格への第一歩です。基本情報技術者の午前問題対策として、以下の参考書が特におすすめ:
初学者向け
- キタミ式イラストIT塾 基本情報技術者
- イラストが豊富で理解しやすい
- IT初心者でも挫折しにくい構成
- 全体像を把握するのに最適
効率重視の方向け
- 出るとこだけ!基本情報技術者[科目A]
- 頻出ポイントに絞った解説
- 短時間で要点を押さえられる
- 忙しい社会人に人気
実際に、文系出身で基本情報技術者に合格したBさんは「最初にキタミ式で全体像を把握してから、出るとこだけで重要ポイントを深堀りする方法が効果的だった」と振り返っています。
重要なのは、複数の参考書に手を出さず、1冊を徹底的にマスターすることです。浅く広く学習するよりも、1冊の内容を完璧に理解する方が確実に力がつきます。
3ヶ月学習プランの具体例
基本情報技術者の午前問題合格に向けた、現実的な3ヶ月学習プランをご紹介します:
1ヶ月目:基礎固め期間
- 参考書1周目(理解度30%でも気にしない)
- 苦手分野の洗い出し
- 用語集の作成開始
2ヶ月目:過去問演習期間
- 過去問5年分を2周
- 間違えた問題の徹底復習
- 計算問題の解法パターン習得
3ヶ月目:総仕上げ期間
- 弱点分野の集中対策
- 模擬試験での実力確認
- 直前1週間は新しい内容に手を出さない
このプランで重要なのは、2ヶ月目からの過去問演習です。基本情報技術者の午前問題は過去問の出題率が高いため、早めに過去問に取り組むことで効率的に得点力を向上させることができます。
スキマ時間活用法(スマホアプリ等)
基本情報技術者の午前問題対策では、スキマ時間の活用が合格の鍵を握ります。特に社会人の方にとって、まとまった学習時間の確保は困難なもの。
おすすめのスキマ時間学習法
- 通勤時間(往復1時間)
- スマホアプリで過去問10~15問
- 基本情報技術者試験問題集アプリが便利
- 昼休み(30分)
- 前日間違えた問題の復習
- 用語の暗記
- 就寝前(15分)
- その日学習した内容の振り返り
- 翌日の学習計画立案
実際に、働きながら合格したCさんは「毎日のスキマ時間で1時間半程度は確保できた。継続することで、まとまった学習時間がなくても十分合格レベルに到達できる」と話しています。
重要なのは、短時間でも毎日継続することです。1日3時間を週末だけやるよりも、毎日30分継続する方が記憶定着の観点から効果的と言えるでしょう。
基本情報技術者午前問題の計算問題対策
基本情報技術者の午前問題で多くの受験者が苦手とするのが計算問題です。しかし、出題パターンは限られており、基本的な考え方を理解すれば確実に得点源にできる分野でもあります。
計算問題を得意にするコツは、公式の丸暗記ではなく、概念の理解にあります。
MIPS計算の基本理解と解法
MIPS(Million Instructions Per Second)は、コンピュータの処理能力を表す指標として基本情報技術者の午前問題で頻出です。
MIPS値の基本的な考え方
- 1秒間に実行できる命令数を百万単位で表す
- 命令実行時間がわかれば計算可能
計算手順
- 1つの命令を実行する時間を確認
- 1秒間に実行できる命令数を計算
- 百万単位に換算
具体例 命令実行時間が20ナノ秒の場合:
- 1秒 = 10億ナノ秒
- 1秒間の命令実行回数 = 10億 ÷ 20 = 5000万回
- MIPS値 = 5000万 ÷ 100万 = 50MIPS
このように、段階的に考えることで複雑に見える計算も確実に解くことができます。
稼働率計算(直列・並列接続)
稼働率計算も基本情報技術者の午前問題で必ず出題される重要分野です。
直列接続の稼働率
- 全ての構成要素が正常に動作する必要
- 計算式:R1 × R2 × R3…
並列接続の稼働率
- どれか1つでも動作すれば全体が動作
- 計算式:1 – (1-R1) × (1-R2) × (1-R3)…
実際の問題例 稼働率0.9のサーバーが2台並列で構成されている場合:
- 稼働率 = 1 – (1-0.9) × (1-0.9) = 1 – 0.1 × 0.1 = 0.99
並列接続により、単体より高い稼働率を実現できることが理解できます。
論理演算(AND、OR、XOR)の攻略法
論理演算は基本情報技術者の午前問題の基礎となる重要分野です。
基本的な論理演算
- AND(論理積):両方が真の時のみ真
- OR(論理和):どちらかが真なら真
- XOR(排他的論理和):どちらか一方のみが真の時に真
攻略のコツ
- 具体的な数値を代入して検証
- 真理値表を頭の中で描く
- 日常語での言い換えを活用
例えば、XORは「AまたはBのどちらか一方だけ」と覚えると理解しやすくなります。
基本情報技術者午前問題の分野別学習ポイント
基本情報技術者の午前問題を効率的に攻略するためには、各分野の特徴を理解し、メリハリをつけた学習が重要です。
出題比重の高いテクノロジ系を中心に、各分野の重点項目をご紹介します。
テクノロジ系の重要分野(データベース、ネットワーク、セキュリティ)
テクノロジ系は基本情報技術者の午前問題の中核を占める分野です。特に以下の3分野は毎回出題されるため、確実に押さえておく必要があります。
データベース分野
- SQL文の基本構文(SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE)
- 正規化の概念(第1~第3正規形)
- ER図の読み方
実際の出題では、「従業員テーブルから特定の条件でデータを抽出するSQL文を選べ」といった形で出題されることが多いです。
ネットワーク分野
- OSI参照モデルの7階層
- TCP/IPプロトコルの基本
- IPアドレスの種類と範囲
ネットワーク分野では、「192.168.1.0/24のネットワークで使用可能なホスト数は?」といった計算問題も頻出です。
セキュリティ分野
- 暗号化技術(共通鍵、公開鍵)
- 認証方式(パスワード、生体認証など)
- マルウェアの種類と対策
セキュリティ分野は時事的な内容も含まれるため、最新の脅威や対策技術についても把握しておくことが重要です。
マネジメント系のポイント(プロジェクトマネジメント)
マネジメント系は出題数こそ少ないものの、確実に得点したい分野です。特にプロジェクトマネジメントは実務でも重要な概念となります。
重要な概念
- PMBOK(プロジェクトマネジメント知識体系)
- WBS(Work Breakdown Structure)
- クリティカルパスの計算
クリティカルパス計算は、基本情報技術者の午前問題で頻出の計算問題です。各作業の最早開始時刻と最遅開始時刻を正確に計算できるよう練習しておきましょう。
ストラテジ系の効率学習法(企業と法務、経営戦略)
ストラテジ系は範囲が広いため、頻出分野に絞った学習が効果的です。
企業と法務
- 著作権法の基本
- 個人情報保護法の概要
- 労働基準法関連
経営戦略
- SWOT分析
- 競争戦略の基本
- 財務指標の計算
ストラテジ系では暗記よりも理解が重要です。各概念がなぜ重要なのか、どのような場面で使われるのかを理解することで、応用問題にも対応できるようになります。
基本情報技術者午前問題の過去問活用法
基本情報技術者の午前問題攻略において、過去問演習は最も重要な学習法です。約70%が過去問からの出題という特徴を活かし、効率的に学習を進めましょう。
過去問学習のコツは、単に問題を解くだけでなく、周辺知識まで深堀りすることです。
基本情報技術者過去問道場の使い方
基本情報技術者過去問道場は、多くの受験者に愛用されている無料の学習サイトです。登録者数34万人を突破し、豊富な機能で効率的な学習をサポートしています。
主な機能と活用法
- ランダム出題機能:苦手分野を重点的に学習
- 分野別出題:特定分野の集中対策
- 学習履歴管理:進捗状況の可視化
効果的な使い方
- 最初は「分野別」で基礎固め
- 慣れてきたら「ランダム出題」で実力試し
- 間違えた問題は「お気に入り」に登録して繰り返し復習
実際に過去問道場を活用して合格したDさんは「通勤時間にスマホで毎日20問ずつ解き続けた。間違えた問題の解説をじっくり読むことで、関連知識も身についた」と話しています。
基本情報技術者試験ドットコムの活用法
基本情報技術者試験ドットコムは、詳しい解説が特徴の老舗学習サイトです。過去問道場と併用することで、より深い理解が得られます。
特徴
- 詳細な解説:なぜその答えになるのかを丁寧に説明
- 分野別整理:体系的な学習が可能
- 関連問題の紹介:類似問題で理解を深化
活用のコツ
- 過去問道場で間違えた問題の詳しい解説を確認
- 分野別ページで体系的な知識整理
- 関連問題で理解度チェック
過去問演習の進め方(間違い直し、復習法)
過去問演習で最も重要なのは、間違えた問題の処理方法です。正解した問題よりも、間違えた問題から多くを学ぶことができます。
効果的な復習サイクル
- 即座の確認:解いた直後に解説を読む
- 1日後の復習:記憶が曖昧になるタイミングで再確認
- 1週間後の再挑戦:同じ問題を再度解く
- 試験直前の最終確認:苦手問題リストの総復習
間違い直しの具体的方法
- なぜ間違えたのかの理由を分析
- 正解の選択肢だけでなく、他の選択肢についても調べる
- 関連する周辺知識もまとめて整理
このような systematic な復習により、単なる暗記ではなく真の理解を得ることができます。
基本情報技術者午前問題の解法テクニックと合格戦略
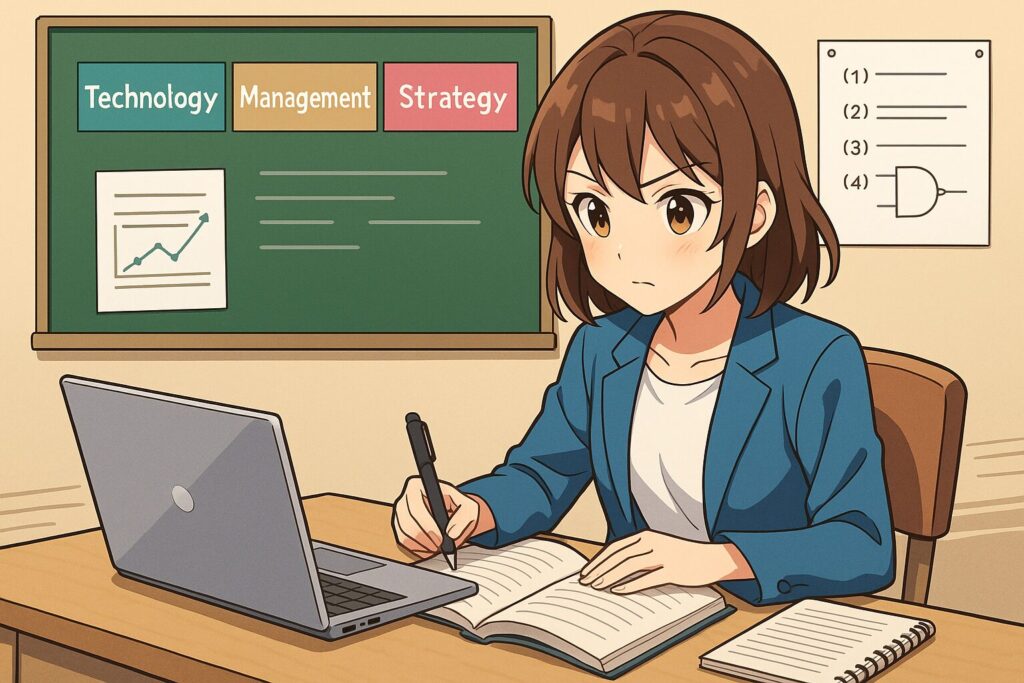
基本情報技術者の午前問題において、知識だけでなく解法テクニックを身につけることで、より確実に合格点を獲得できます。
ここでは、試験当日に役立つ実践的な戦略をご紹介いたします。
基本情報技術者午前問題の時間配分戦略
基本情報技術者の午前問題では、90分で60問を解く必要があります。時間に余裕があるとはいえ、効率的な時間配分を心がけることで、見直し時間を確保し、ケアレスミスを防ぐことができます。
戦略的な時間配分こそが、合格への近道と言えるでしょう。
基本問題・計算問題・知識問題の時間配分
基本情報技術者の午前問題を問題タイプ別に分類し、それぞれに適切な時間を配分することが重要です。
推奨時間配分
- 基本知識問題(40問):40分(1問1分)
- 計算問題(15問):30分(1問2分)
- 応用・判断問題(5問):10分(1問2分)
- 見直し時間:10分
基本知識問題は、用語の意味や基本的な概念を問うもので、知っていれば即座に答えられます。一方、計算問題は手順を踏んで解く必要があるため、やや時間をかける価値があります。
実際に2024年春期に合格したEさんは「基本問題を素早く処理することで、計算問題にじっくり時間をかけることができた。結果的に高得点を取ることができた」と振り返っています。
分からない問題の飛ばし方
基本情報技術者の午前問題では、分からない問題に時間をかけすぎるのは得策ではありません。効率的な「飛ばし方」を身につけることが重要です。
飛ばす判断基準
- 30秒考えてもアプローチが思い浮かばない
- 計算が複雑で時間がかかりそう
- 見たことのない専門用語が多い
飛ばした問題の管理法
- 問題番号をメモしておく
- 推測で解答をマークしておく(空欄は避ける)
- 見直し時に再挑戦
四択問題では、何も分からなくても25%の正答確率があります。完全に諦めるのではなく、推測であっても解答をマークしておくことが大切です。
見直し時間の確保方法
基本情報技術者の午前問題で高得点を狙うためには、見直し時間の確保が不可欠です。
見直しで確認すべきポイント
- マークミスの確認:選択した番号と問題番号の一致
- 計算の再確認:特に桁数や単位の間違い
- 飛ばした問題への再挑戦:新たな視点で問題を見直し
見直し時間確保のコツ
- 基本問題を素早く処理する習慣をつける
- 迷った問題は一旦決めて先に進む
- 最低10分の見直し時間は確保する
見直しにより、平均して2~3問の正答数向上が期待できます。これは合格ラインを考えると非常に大きな効果と言えるでしょう。
基本情報技術者午前問題の消去法と解法テクニック
基本情報技術者の午前問題は四択形式のため、消去法を効果的に活用することで正答率を大幅に向上させることができます。
完璧な知識がなくても、戦略的なアプローチで正解にたどり着くことが可能です。
選択肢の絞り込み方法
基本情報技術者の午前問題で効果的な選択肢絞り込みのテクニックをご紹介します。
段階的絞り込み戦略
- 明らかに間違っている選択肢を除外
- 問題文のキーワードと矛盾する選択肢を除外
- 残った選択肢から最も適切なものを選択
具体例:データベースの正規化に関する問題
- 選択肢A:「第1正規化で重複する行を削除する」→ 間違い(重複削除は正規化の目的ではない)
- 選択肢B:「第2正規化で部分関数従属を解消する」→ 正解の可能性
- 選択肢C:「第3正規化で推移関数従属を解消する」→ 正解の可能性
- 選択肢D:「正規化により必ずデータ量が削減される」→ 間違い(必ずしも削減されるわけではない)
このように、明らかに間違っている選択肢を先に除外することで、正答率を50%まで上げることができます。
具体的数値代入による検証法
論理演算や計算問題では、具体的な数値を代入して検証する方法が非常に効果的です。
論理回路問題での活用例 問題:「AとBの入力に対する出力が○○となる回路はどれか」
解法手順:
- A=0, B=0を代入
- A=0, B=1を代入
- A=1, B=0を代入
- A=1, B=1を代入
- 各選択肢で計算し、問題文の条件と一致するものを選択
この方法により、複雑な論理回路も確実に解くことができます。
略語・専門用語の覚え方
基本情報技術者の午前問題では、多くの略語や専門用語が出題されます。効率的な暗記法をマスターしましょう。
効果的な暗記テクニック
- 語源からの理解
- CPU = Central Processing Unit(中央処理装置)
- RAM = Random Access Memory(ランダムアクセスメモリ)
- 関連付けによる記憶
- HTTP(HyperText Transfer Protocol)とHTTPS(HTTP Secure)を一緒に覚える
- 実際の使用場面をイメージ
- API(Application Programming Interface)→ アプリ同士をつなぐ窓口
暗記だけでなく、その用語が実際にどのような場面で使われるかを理解することで、応用問題にも対応できるようになります。
基本情報技術者午前問題の苦手分野克服法
基本情報技術者の午前問題では、多くの受験者が共通して苦手とする分野があります。これらの分野を効率的に克服することで、大幅な得点アップが期待できます。
苦手分野の克服は、合格への最短ルートと言えるでしょう。
数学・計算問題が苦手な人向けの対策
基本情報技術者の午前問題で最も苦手意識を持たれやすいのが計算問題です。しかし、出題パターンは限られており、適切な対策により確実に得点源にできます。
計算問題攻略の3ステップ
- 基本公式の理解(暗記ではなく意味の理解)
- 解法パターンの習得(同じタイプの問題を繰り返し練習)
- 時間短縮テクニック(効率的な計算方法の習得)
具体的な対策例:2進数計算
- 10進数から2進数への変換:2で割り続けて余りを逆順に並べる
- 2進数から10進数への変換:各桁に2のn乗をかけて合計
- 2進数同士の計算:筆算の要領で計算
文系出身で数学に苦手意識があったFさんは「最初は2進数すら分からなかったが、毎日10分ずつ計算練習を続けることで、試験本番では計算問題が得点源になった」と話しています。
重要なのは、完璧を目指さず、基本パターンを確実にマスターすることです。
アルゴリズムの基礎理解
基本情報技術者の午前問題では、アルゴリズムに関する基礎的な問題も出題されます。プログラミング経験がない方でも、基本概念を理解することで対応可能です。
押さえるべき基本概念
- 配列とリスト:データの格納方法
- ソートアルゴリズム:データの並び替え方法
- 探索アルゴリズム:目的のデータを見つける方法
- スタックとキュー:データの取り出し順序
理解のコツ
- 身近な例で考える
- ソート:本棚の本を著者名順に並べる
- 探索:辞書で単語を調べる
- スタック:積み重ねた皿(後入れ先出し)
- 図やイラストを活用
- 抽象的な概念を視覚的に理解
- 処理の流れをステップごとに追跡
プログラミング未経験だったGさんは「アルゴリズムは難しそうに見えたが、身近な例で考えることで理解できた。午前問題レベルなら基本概念がわかれば十分対応できる」と語っています。
ハードウェア・システム構成の攻略
ハードウェアやシステム構成は、目に見えない部分が多いため苦手とする方が多い分野です。しかし、基本的な仕組みを理解すれば決して難しくありません。
重要な構成要素
- CPU:コンピュータの頭脳(計算処理)
- メモリ:一時的なデータ保存場所
- ストレージ:永続的なデータ保存場所
- 入出力装置:人とコンピュータの橋渡し
理解を深めるアプローチ
- 身の回りの機器と関連付ける
- スマートフォンやパソコンの構成を意識
- 各部品の役割を実体験と結びつける
- 性能指標の意味を理解
- クロック周波数:処理の速さ
- メモリ容量:同時に扱えるデータ量
- ストレージ容量:保存できるデータ量
実際の学習では、理論だけでなく実物を意識することで理解が深まります。
基本情報技術者午前問題の直前対策と当日準備
基本情報技術者の午前問題において、試験直前の対策と当日の準備は合格を左右する重要な要素です。
これまでの学習成果を最大限に発揮するための戦略をご紹介します。
1週間前からの復習スケジュール
試験1週間前からは、新しい内容に手を出すのではなく、これまでの学習内容を確実に定着させることに集中しましょう。
1週間前スケジュール例
- 7日前~5日前:苦手分野の総復習
- 4日前~2日前:過去問の間違い問題を再演習
- 1日前:軽い復習のみ、早めの就寝
具体的な復習内容
- 用語集の最終確認
- 自作した用語リストを総点検
- 特に略語と正式名称のセット確認
- 計算問題の解法パターン確認
- MIPS、稼働率、論理演算の公式
- 実際に手を動かして確認
- 頻出分野の重要ポイント整理
- データベース、ネットワーク、セキュリティの基本事項
- 過去問で繰り返し出題されている内容
直前期に焦って新しい参考書に手を出すのは逆効果です。これまでの学習内容を確実に自分のものにすることが重要になります。
当日の持ち物と会場での注意点
基本情報技術者の午前問題はCBT方式のため、従来のペーパーテストとは異なる準備が必要です。
必須の持ち物
- 受験票(メールまたは郵送で届いたもの)
- 身分証明書(運転免許証、パスポートなど写真付き)
- 筆記用具(計算用のメモ用)
- 腕時計(会場に時計がない場合もあるため)
会場での注意点
- 30分前には到着
- 会場の雰囲気に慣れるため
- 受付手続きの時間を考慮
- トイレは事前に済ませる
- 試験中の中断は時間ロスとなる
- 集中力維持のため
- 緊張した時の対処法を準備
- 深呼吸や軽いストレッチ
- ポジティブな自己暗示
実際に受験したHさんは「会場に早めに着いて、コンピュータの操作に慣れる時間があったおかげで、本番では落ち着いて取り組めた」と話しています。
CBT方式の操作方法と画面構成
基本情報技術者の午前問題は、2023年からCBT(Computer Based Testing)方式で実施されています。事前に操作方法を理解しておくことが重要です。
基本的な操作方法
- 問題の表示
- 画面左側に問題文、右側に選択肢
- スクロールで問題全体を確認
- 解答の選択
- 選択肢をクリックで選択
- 選択を変更する場合は別の選択肢をクリック
- 問題間の移動
- 「次へ」「前へ」ボタンで移動
- 問題番号を直接クリックして移動も可能
便利な機能
- フラグ機能:見直したい問題にマークを付ける
- 電卓機能:画面上の電卓を使用可能
- 残り時間表示:常に時間を意識できる
注意すべき点
- 画面の文字サイズが小さい場合は調整可能
- マウス操作に慣れていない場合は事前練習が効果的
- 最後に必ず全問題の解答状況を確認
CBT方式に慣れるため、IPA(情報処理推進機構)の公式サイトで体験版を試してみることをおすすめします。
基本情報技術者午前問題から科目B対策への橋渡し
基本情報技術者試験では、午前問題(科目A)に合格した後、科目Bにも挑戦する必要があります。午前問題で身につけた知識を効果的に科目B対策に活かす方法をご紹介します。
午前問題の学習は、科目B合格への重要な土台となります。
午前問題の知識が科目Bに活かされる分野
基本情報技術者の午前問題で学習した内容は、科目Bの多くの分野で直接的に活用できます。
直接活用できる分野
- アルゴリズムとデータ構造
- 午前で学習したソート、探索の基本概念
- スタック、キュー、木構造の理解
- プログラミング言語の基礎
- 変数、配列、条件分岐、繰り返しの概念
- 関数、プロシージャの基本理解
- 情報セキュリティ
- 暗号化技術、認証方式の知識
- マルウェア、脆弱性対策の基本
活用のコツ
- 午前問題の用語集を科目B学習でも参照
- 基本概念の理解を応用問題解決に活用
- 午前の計算能力を科目Bのアルゴリズム理解に応用
科目A(午前)に合格したIさんは「午前で学習したアルゴリズムの基本概念が科目Bのプログラム読解にとても役立った。基礎がしっかりしていると応用も理解しやすい」と振り返っています。
科目A免除制度のメリット・デメリット
基本情報技術者試験には、科目A免除制度があります。この制度を利用するかどうかは、個人の状況に応じて判断する必要があります。
科目A免除制度とは
- IPA認定の講座を受講し、修了試験に合格すると科目Aが1年間免除
- 科目Bのみの受験で基本情報技術者試験に合格可能
メリット
- 学習時間の短縮
- 科目Bの対策に集中できる
- 特にアルゴリズムが苦手な場合は効果的
- 合格確率の向上
- 一度に両方合格する必要がない
- 段階的に合格を目指せる
- 再受験時のリスク軽減
- 科目Aは免除期間中は受験不要
デメリット
- 講座受講費用
- 通常3万円~10万円程度の費用が必要
- 免除期間の制限
- 免除期間は1年間のみ
- 期間内に科目Bに合格する必要
- 基礎知識の曖昧さ
- 科目Aの知識が不十分だと科目Bで苦労する可能性
利用を検討すべき人
- 確実に合格したい人
- 学習時間が限られている人
- 会社の研修制度が利用できる人
午前突破後の科目B学習計画
基本情報技術者の午前問題に合格した後は、科目B対策に移行します。効率的な学習計画を立てることが重要です。
科目B学習の基本方針
- 午前の知識を基盤とする
- 用語や基本概念は午前で習得済み
- 応用・実践面に重点を置く
- アルゴリズム理解に重点を置く
- 科目Bの中心的な出題分野
- プログラムの読解・トレース能力を向上
- 情報セキュリティの実践的理解
- 午前の知識をより深く、実践的に学習
具体的な学習スケジュール(2ヶ月間)
1ヶ月目:基礎固め
- 疑似言語の読み方をマスター
- 基本的なアルゴリズムの理解
- IPAのサンプル問題を解く
2ヶ月目:実践演習
- 過去の午後問題(アルゴリズム分野)を演習
- 時間を意識した問題演習
- 弱点分野の集中対策
学習のポイント
- 午前の学習ノートを科目B学習でも活用
- 新しい概念は午前の知識と関連付けて理解
- 定期的に午前の重要事項も復習(忘れ防止)
午前→科目Bと段階的に合格したJさんは「午前でしっかり基礎を固めたおかげで、科目Bでは応用に集中できた。段階的なアプローチが自分には合っていた」と話しています。
まとめ
基本情報技術者の午前問題(科目A)攻略の鍵は、過去問中心の学習と効率的な時間配分にあります。
約70%が過去問から出題されるという特徴を活かし、基本情報技術者過去問道場などの学習ツールを効果的に活用しましょう。計算問題やアルゴリズムなどの苦手分野も、基本概念の理解と反復練習により確実に克服できます。
重要なのは、完璧を目指さず、確実に60%以上の得点を確保することです。全ての問題を理解する必要はありません。頻出分野を重点的に学習し、戦略的に合格点を目指してください。
CBT方式の導入により、いつでも受験できるようになった基本情報技術者試験。十分な準備をして、自信を持って試験に臨みましょう。
基本情報技術者の午前問題合格は、IT業界でのキャリア構築における重要な第一歩です。本記事でご紹介した学習法と解法テクニックを活用し、ぜひ合格を勝ち取ってください。





コメント